演奏のトレーニング、つまり「思うように体が動いて演奏できるようになるためのトレーニング」とは、「筋肉を鍛えること」ではなく、『脳を鍛えること、それと神経を鍛えること』すなわち『神経ネットワークを鍛えること』、これにほかならない。
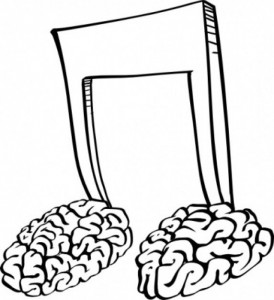 (以下演奏のトレーニングは単に「練習」とする)
(以下演奏のトレーニングは単に「練習」とする)
筋肉を鍛えても無駄。筋力トレーニングは、演奏の場合はむしろ害になることもある。神経を鍛えればそれに必要な筋力は自然に付いてくるようになるものだろう。無駄な筋肉は動きを阻害するだけである。筋力が無くて演奏出来ないことがあれば、まずは「脳が理解すること」を優先させるべきだろう。
筋肉を動かすのは脳からの命令を伝える神経なわけであり、その送受信がうまくいくようにするために様々なトレーニングを行うということである。面白いことに、これは実際に筋肉を動かしているかどうかはどうやら関係無いらしい。イメージ・トレーニングしているアスリートにセンサーをつけて計測してみると、実際に動作している時と同じ信号が脳から発せられていたという話も聞いたこともある。おそらく事実だろうと思う。
私を含め、演奏の練習を見ているとわかるのだが、漫然と練習している人(ただ繰り返している、つまりそれをトレーニングだと思い込んでいる人)は、あまり伸びない。何を練習するかがわかっている人(理解すべきことに集中できる人)は、あまり練習時間を確保出来ていなくても、なぜか伸びはいい。
一般の筋トレにしても、その鍛える筋肉を意識してトレーニングしないと効果は低いと言われている。その理由もわかる気がする。
スポーツ全般のトレーニングにおいても同じだと思う。ただ演奏などと違うのは、筋肉そのものを鍛える要素も大きいというだけだ。
で、この神経ネットワークは、使っていないとどんどん衰える。
 私ごとで恐縮だが…。
私ごとで恐縮だが…。
最近、趣味でドラムを叩くことがあるのだが…先日もドラムを始めて間もない人に驚かれた。「ずっと叩いてなかったんでしょ?いつも練習してるんじゃないんでしょ?なんで叩けるの?」と。
ドラムをやっていたのはわずか(実質3年くらいだと思う)であるが、その後もずっと私の中ではドラムが鳴り続けている。いろんな曲を聴けば自然とドラムを叩いているような感覚になる(指先を動かすことはよくある)。年を経るに従い、若いころには気が付かなかったプレイの細かい点が聴こえるようになる。「こう叩いているんだな」とイメージが出来る。それが積み重なって今に至っている。
「体が覚えている」とよく言われるが、その実は「脳が覚えている」ことにほかならないわけであり。実際には覚えているだけではなくて、ずっと頭のなかでトレーニングがなされてきたわけで。
なぜ練習していないのに神経ネットワークが衰退していないか、それはほとんど無意識にイメージ・トレーニングを重ねていたことにあるのだろうと思う。
ところで。
上手な人が演奏しているそばで演奏すると、その雰囲気に飲まれてうまくなったような気がする。好きなミュージシャンのライブにいったあとも妙にうまく演奏できたりする。が、これはつられて脳が反応を始めたということだろうと思う。脳には「ミラーニューロン」という神経細胞があるが、この作用では無いだろうかと推測している。
(ちなみにミラーニューロンとは、ごくわかりやすく言えば隣の人があくびをしたら自分にも移ったという、あの現象のこと。感情なんかも伝播するのはミラーニューロンのせいだとも言われる。)
この点で、「教則ビデオ」というのは非常にいいアイテムだと思う。そこには実際に教師はいないが、演奏の仕方・プレイの細かい点・なにより雰囲気を良くみることで、自分の中で脳・神経のネットワークが活性化する。私も憧れるプレイヤーの演奏をビデオで見たあとなどは、調子がいい。ビデオを見てから練習できる時間があるなら、そうしたいのは山々であるが…。
ではこれ、実際にその場で「教えてもらう」と上手く働かないことがある。自分が見て、自分で解釈しなければいけないようだ。教えてもらうと大抵は最初に陥るのは『混乱』である。だから、下手に教える側がその場にいると上手く行かないことも多いと思う。教えるのではなく、感じさせることなのだろうと。
こうした練習において重要なのは、自分より上手く演奏できる人は何が違うんだろう?と『考える』こと。しかしもっと重要な事は、意識に上らない無意識下で『感じ取る』こと。『教えてもらう』こと自体に実質的な意味はなく、見て感じ取ることが教わるということなのでは無いだろうかと思う。更に言及すれば、理解とは「論理的理解(言葉で表せる)」ものと「非論理的理解(言葉で説明できない)」ものがあるということも確かだと思う。
パターンやフレーズを練習するにしても、それがどういう仕組み(譜割りなど)になっているか分析し理解してやっている人は伸びるし、なんとなくやっている人は伸びない。分析し理解することはとてもエネルギーが必要だから、ついただ漫然と練習してしまう。(私もよくやってしまう。)
おそらく音楽教室などのレッスンでも、理解させてから実際に演奏させてみるのと、ただ繰り返し体を動かさせているのとでは、明らかに学習・上達スピードが違うだろうと推測できる。もっとも、理解させる方法はなかなか十把一絡げにはいかないもので、そこが難しいのだろうということも推測できる。(だから、「とりあえずやってみようか」という方法も正しい訳で。)
私も自分の演奏能力にはがっかりすることは多々なので、全くもって偉そうなことは言えないのではあるが…。
繰り返し繰り返し体を動かしているだけでも、なんとか出来るようにはなる。効果が無いとはいわないが、効率が悪い。人生にそこまでの余裕時間と根気のある人はほとんどいないだろう。(だから挫折してやめてしまう。)
つまり、演奏能力の向上に必要なのは、『集中力』とそれを支える『持久体力』。
結局はそれが才能や能力の違いということになるのだろう。(もちろん、能力を伸ばすために必要な要素はこれだけではないが。)
この記事のサブタイトルに「理解と実践」にしたのも意味がある。一般的には「理論と実践」という言葉が闊歩していると思うが、その実は「理解と実践」だと私は思う。理論を”勉強して知識に”したところで、理解していなければあまり意味がないということである。
ただ、理解とは表層意識だけでなく無意識の領域での理解もあるということで、その代表がミラーニューロンの例で述べたことである。無意識はコントロールが難しいのだけれど…。
後記
おかげさまでいくらかバーンアウトから脱出しており、曲も数曲モチーフが出来始めている。
今年は平穏な気候が続いているような気がする北海道富良野。これを執筆したのは2014年11月30日であるが、本州の晩秋によく似た様子が周りに伺え、懐かしいとさえ思った。とはいえ、これも数日だろう。きっと第一回目の極寒の日が来週にもやって来るのではないかと、ちょっとヒヤヒヤして毎日を過ごしている。
既に春が待ち遠しい。北海道民病になっているようだ。

コメントを残す